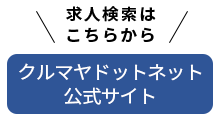近年、日本の自動車整備業界では整備士不足が深刻な問題となっています。八王子にある自動車整備学校では(2024年度)415名が卒業式を迎えるそうですが、新卒整備士を採用したくても採用できない企業が非常に多くなっています。日本の自動車整備士の人数は技術の進化とともに求められるスキルが高度化する一方で、整備士の高齢化や若手の減少により、業界全体に大きな影響を与えています。本コラムでは、整備士不足の現状と原因、業界の取り組み、そして未来の展望について考察します。
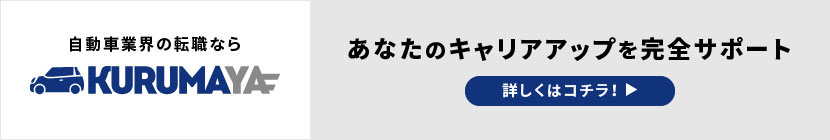
1.深刻化する自動車整備士不足の現状

日本自動車整備振興会のデータによると、国内の自動車整備士の数は年々減少しており、特に若年層の整備士が不足しています。現在の整備士の平均年齢は40歳を超えており、50代・60代のベテラン整備士が多くを占めています。このままでは、熟練した技術を持つ整備士が引退した際に、そのノウハウを継承する人材が不足し、業界全体の技術力が低下する可能性が懸念されています。
現場では、整備士一人ひとりの負担が増加しており、「人手が足りず、休みが取れない」「新人が定着せず、常に人材不足を感じる」といった声が多く聞かれます。特に、繁忙期には1日中作業に追われ、休憩をまともに取ることすら難しいこともあります。加えて、技術の進化に伴い、EV(電気自動車)やハイブリッド車、自動運転技術を搭載した最新車両の整備には、新たな知識とスキルが求められます。しかし、多忙な業務の中で十分な研修時間を確保するのは難しく、現場の整備士は常に学び続けなければならないプレッシャーにさらされています。
また、人手不足による納期の遅れや、過剰な業務負担による離職が相次ぎ、結果として整備士不足がさらに深刻化する悪循環に陥っています。こうした状況が続けば、整備業界の持続可能性そのものが危ぶまれる事態となりかねません。
このような現状を打開するためには、整備士の待遇改善や業務の効率化が急務となっています。次章では、整備士不足の具体的な原因について詳しく見ていきます。
2.整備士不足の原因

- 若者の自動車離れと整備士職の人気低下
近年、若者の自動車への関心が低下しており、整備士という職業に憧れる人も減っているようです。また、「きつい・汚れる・給料が安い」という3Kのイメージが根強く、整備士という職業を選ぶ人が少なくなっています。最近は「暑い・寒い」という環境面もポイントになっているようです。 - 労働環境の問題
自動車業界は全体的に、長時間労働や休日の少なさが問題視されています。一般的な企業の土日祝休み(年間休日120日以上)に対して、整備工場は100~110日の会社が多いようです。また、ディーラーや民間整備工場では繁忙期に業務が集中し、過重労働となるケースが多く、若手の離職率が高いのが現状です。 - 外国人整備士の受け入れの遅れ
少子高齢化が進む日本では、外国人労働者の活用が不可欠ですが、自動車整備士業界ではまだ十分に進んでいません。技能実習制度を利用して外国人整備士を受け入れる企業も増えてきましたが、日本語の壁や資格取得のハードルが高いのが現状です。自動車整備士として働きたい特定技能1号・特定技能2号、就労ビザなどの資格を持つ外国人にとっていかに魅力的な会社と感じていただく事も非常に大切です。
3.業界の取り組みと解決策

- 給与・待遇の改善
整備士の給与は、他の技術職と比べて低い傾向にあると言われています。しかし、近年では企業側も待遇を改善し、インセンティブ制度を導入するなどの動きが進んでいます。特に、大手ディーラーや大手中古車販売店では福利厚生の充実やキャリアアップの機会を増やすことで、離職率の低減を図っています。 - 働き方改革の推進
労働時間の短縮や休日の増加を図る企業も増えています。また、業務のデジタル化により、作業の効率化を進めることで、整備士の負担を軽減する動きもあります。管理システムや作業効率化のための自動設備を導入する企業は求職者からも人気があります。 - 教育・研修制度の充実
整備士に求められるスキルが高度化する中、専門学校や企業内研修の充実が重要になっています。特に、EVや先進運転支援システム(ADAS)に対応する研修を強化することで、若手整備士の育成を促進しています。 - 外国人整備士の積極的な受け入れ
前章でもお伝えしましたが、整備士不足を補うため、外国人整備士の受け入れを進める動きも活発化しています。特定技能制度を活用し、即戦力として採用する企業が増えています。また、日本語教育や技術研修を強化することで、外国人整備士がスムーズに現場で活躍できる環境を整えています。
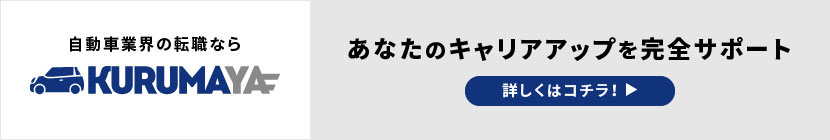
4.未来の整備士業界の展望

整備士不足を解決するためには、業界全体の構造改革が求められます。今後の展望として、以下のような動きが期待されます。
1. AIやロボットの活用
AIを活用した自動診断システムやロボットによる整備作業の一部自動化が進めば、整備士の負担が大幅に軽減される可能性があります。
2. デジタルツールの導入
クラウドを活用した整備履歴管理やリモート診断システムの導入により、効率的な整備業務が可能になります。これにより、少ない人員でも高品質な整備サービスを提供できるようになるでしょう。
まとめ
自動車整備士不足は業界全体にとって大きな課題ですが、働き方改革や教育の充実、外国人整備士の活用など、さまざまな対策が進められています。今後は、テクノロジーの導入と人材育成を両立させることで、持続可能な整備業界を構築することが求められるでしょう。
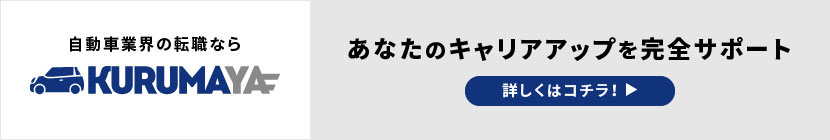
【自動車整備士の求人】
外国籍歓迎の求人
https://kurumaya.net/detail/5494
https://kurumaya.net/detail/5487
https://kurumaya.net/detail/5484